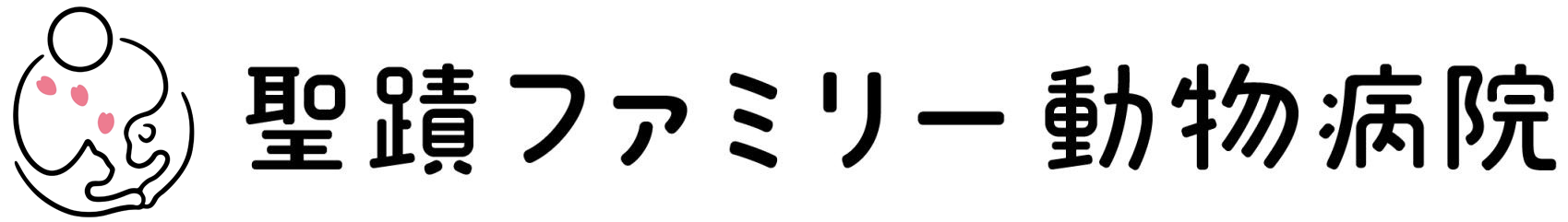雄猫の尿道狭窄、尿道閉塞
【概要】
尿道閉塞とは、尿道内で結石や栓子と呼ばれるミネラルや炎症産物が混ざって
固まった異物が詰まってしまい尿が出せなくなってしまう病気です。
また尿道狭窄とは尿道が狭くなってしまう病気であり、膀胱炎や尿道炎、尿道閉塞を
繰り返していると尿道の粘膜で炎症が起きて、肥厚して狭くなると考えられています。
尿道閉塞を起こしてしまうと、トイレに行くが尿が全く出ない、排尿姿勢を取りながら
苦しそうに鳴いている、といった症状が見られたり、また尿が出ない状態が持続すると
合併症として急性腎障害を引き起こすことがあり、元気や食欲の低下、嘔吐などの症状が
見られたり、最悪の場合亡くなってしまうこともあります。
雄猫では犬や雌猫と比較して尿道がもともと狭いため、
尿道狭窄や尿道閉塞を起こしやすいと言われています。
【診断】
尿道閉塞の診断には、上記の臨床症状や触診による膀胱内の畜尿の確認、レントゲン検査や
超音波検査などの画像検査による総合的な評価が必要になります。
最終的に尿道閉塞が疑われる場合は尿道にカテーテルという管を挿入し、カテーテルがスムーズに
膀胱内に入らず突っかかってしまうことが確認されたら閉塞していることが確定となります。
閉塞していたものが何かを判断するために、閉塞を解除したのちに尿検査を実施することも必要と
なります。
また元気や食欲が低下している場合には、同時に急性腎障害を引き起こしている可能性があるため、
血液検査で全身状態を評価することもあります。
【治療】
各種検査により尿道閉塞が疑われる場合は、直ちに閉塞の解除を試みます。
方法としては尿道にカテーテルを挿入し、生理食塩水を用いて尿道から膀胱に向かって水圧をかけて、
結石や栓子などの閉塞物を膀胱内に押し戻すという方法を用います。
これらの処置は麻酔をかけずに行うこともありますが、無理に処置を行うと
尿道を傷つけてしまうリスクがあるため、猫の性格や状態によっては鎮静剤という
少し落ち着かせる注射をして実施することもあります。
同時に急性腎障害を引き起こしている場合は、点滴などの入院治療が必要なケースもあり、
また尿道閉塞を繰り返していて尿道狭窄を疑う場合は、再発防止のために手術をご提案することも
あります。
【当院での取り組み】
尿が出ないという症状だけでは、膀胱炎による頻尿症状なのか、尿道閉塞による症状なのか
判断が難しいことが多々あるので、当院ではまず飼い主様の稟告をしっかりと聴取し、
ご自宅での排尿の様子や元気や食欲などの一般状態を丁寧にお伺いします。
そして身体検査を確実に行い、膀胱内に尿が溜まっているか、お腹の痛みがないかなどを確認します。
その上で尿道閉塞が疑われる場合には、画像検査やカテーテルでの疎通確認を行います。
また治療の項で記載の通り、処置を行う際には猫の負担を考慮して、無理に処置を行うことはせず、
必要に応じて鎮静剤を投与します。
また一度閉塞を解除できたとしても、尿道の炎症や狭窄によりすぐに再閉塞してしまう危険性が
高い場合には、挿入したカテーテルを固定した状態で数日~一週間程度の入院治療をご提案することも
あります。
当院では処置を行う際や治療方針の決定など、全てにおいて事前に飼い主様とよくご相談を
させていただきます。
【通院・入院の予測】
元気や食欲などの一般状態に問題がなく、尿道閉塞が比較的短時間で解除できる場合は、
通院治療が可能なこともありますが、急性腎不全を併発していたり尿道狭窄により再閉塞するリスクが
高い場合は、入院治療をご提案することもあります。
通院治療の場合は消炎剤や抗生剤の飲み薬を処方し、ご自宅での排尿の様子をよく見ていただき、
再閉塞が疑われる場合にはすぐに病院に連れてきていただくようお伝えしています。
また入院治療の場合は、猫の体調や排尿の状態にもよりますが数日~一週間程度の点滴治療、
カテーテル管理が必要なこともあります。
猫の性格や飼い主様のご要望などを踏まえて、それぞれの患者様・飼い主様に合った最善の治療方法を
一緒に考えていきます。
【費用の予測】
診断までの費用は猫の状態や検査内容にもよりますが、一般的には1.5~3万円程度です。
通院治療の場合は、内服薬一週間分で2000~3000円になります。
一方で入院治療の場合は一泊あたり1.5~2万円程度で、入院期間によっては10~15万円程度に
なることもあります。
また尿道閉塞を繰り返しており手術が必要な場合は、入院費や手術費などを含めて20~30万円になります。
なお、この費用は猫の状態や体重により異なる可能性がありますので、診察された獣医師と詳しくご相談
下さい。