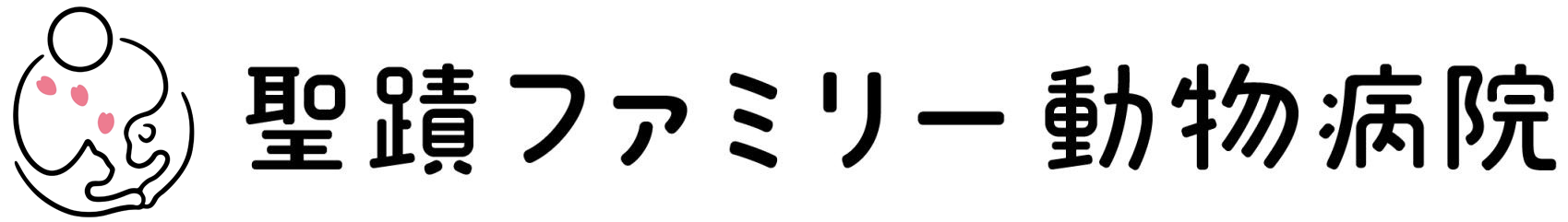猫の糖尿病
【概要】
糖尿病とは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が低下したりインスリンの作用不全が原因で高血糖が持続し、様々な代謝異常を引き起こす病気です。糖尿病の発症原因としては、肥満や膵炎、またステロイドホルモンの分泌異常のクッシング症候群などがあります。症状としては、初期には飲水量や尿量の増加、多食、体重減少などが見られますが、高血糖が持続し体のミネラルバランスが乱れる(糖尿病性ケトアシドーシス)と、元気や食欲の低下、嘔吐や下痢、脱水などが起こり命に関わる危険な状態に陥ることもあります。
【診断】
飲水量や尿量の増加、体重減少などの臨床症状に加えて、身体検査や血液検査、尿検査などで総合的に診断します。元気や食欲が低下している場合は、レントゲン検査や超音波検査度を同時に行うこともあります。また糖化アルブミンという、2~4週間前までの平均血糖値を反映できる数値を測定することで、血糖値が持続的に高値であったかどうかも判断することができます。診断において重要な点は、糖尿病か否かという点と、進行した糖尿病でミネラルバランスが乱れている(糖尿病性ケトアシドーシス)か否かという点にありますので、ケトン体が検出されるかどうかを血液検査や尿検査で確認することも重要になります。
【治療】
治療法は病気の進行度により異なります。糖尿病の治療は基本的にはインスリンの注射で行いますので、食欲がありご自宅でのインスリン注射が可能な場合は一日1~2回注射を実施していただき、通院で定期的に血糖値を測定します。ただし、初期治療の場合にはインスリンの適正量を決めるために半日~1日入院していただくこともあります。また食事に関しても、糖質を抑えた糖尿病用の療法食がありますので、可能であればそちらに切り替えていただくことを勧めております。一方、糖尿病の進行に伴い元気や食欲が低下し、各種検査で糖尿病性ケトアシドーシスに陥っていると判断した場合は、一週間程度の入院で集中治療を行うこともあります。
【当院での取り組み】
飲水量の増加や体重減少など糖尿病が疑われる場合は、血液検査などの積極的な検査をご提案いたします。猫では1日に1キロあたり50ml以上飲水している場合は飲水量が多いと考えられますので、飲水量の増加が疑わしい場合はご自宅での計量を勧めております。また猫では人と同様に肥満が糖尿病の要因の一つと考えられているため、定期的な健康診断を通して食事のご指導やダイエット方法などをご案内することもございます。
【通院・入院の予測】
病気の進行度や体調にもよりますが、食欲や元気がありご自宅でのインスリン投与が可能な場合は通院で治療を行うことができます。初めの1-2ヵ月間は、血糖値が落ち着くまで1-2週間に一回診察させていただき血糖値を測定します。その後体調や血糖値が安定してきたら、2-3か月おきに定期健診を行います。一方、糖尿病の進行に伴い元気や食欲が低下している場合は、点滴や食事管理のために一週間程度の入院で集中治療を行うこともあります。
【費用の予測】
一般的には診断までの費用は2~3万円程度です。診断後の定期的な血液検査は一回あたり3000~5000円で、インスリンの注射液や針を処方する場合は一カ月5000円~1万円程度です。また入院治療が必要な場合は一日あたり2~3万円程度になります。なお、この費用は猫ちゃんの状態や体重により異なる可能性があります。この病気は治療期間が長期にわたることが一般的です。そのため、治療に伴う費用や投薬が猫ちゃんや飼い主様にとって負担にならないよう、診察を行った担当獣医師としっかりと相談しながら進めていきます。